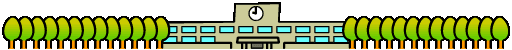 |
| �r�W�l�X�T�|�[�g�s�n�o�� | �Q�� |
|
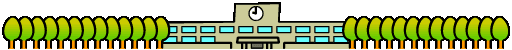 |
| �r�W�l�X�T�|�[�g�s�n�o�� | �Q�� |
|
| �@�]�ʐ��w�Z�@ |
| �h�m�c�d�w |
| �͂��߂��@ |
| ���j�����R�s�[�ɂ��� |
| �Ηj�������ɂ��� |
| ���j�����v���X�`�b�N�ɂ��� |
| �ؗj���� |
| ���j���� |
| �y�j���� |
| ���j���� |
| �����Ԃ�傫���o�܂������i�j�A�Z���̖����ł��B��낵�����肢�������܂��B�i���̊w�Z�̐搶�́A���ЂƂ肾���ł��B�j �u�����A�@�ނ͑��������A���͂ǂ�����Ⴀ�����B�v�Ƃ܂ł͌���Ȃ��Ă��A�݂Ȃ���̋��ʂ����C�����Ƃ��ẮA�͂����Ă��܂��������ȁ`�H(�S�z�j�A�Ƃ����̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B ��̃r�W�l�X�u���ł�����\���グ�܂������A�r�W�l�X�Ƃ����͎̂d�������Ă̂��̂��˂ŁA��͂�c�Ƃ���ԏd�v�Ƃ������Ƃɂ͕ς��͂���܂���B �������Ȃ���A����Ɓi�]�ʂ��܂߂āj�Ƃ����̂́A�����Ƃł�����A�{���I�ɂ͕i�����ł��B������d�����f�d�s���Ă��A�s�Ǖi��n���Ă��܂��ẮA�M�p�����������ŁA������͗���d�������Ȃ��Ȃ�܂��B ���̃X�N�[���́A�c�Ƃ̂��Ƃ͂��Ă����āA�Z�p�ʁA����ʂɂ��āA�v������m���ƋZ�p��g�ɒ����Ă����������Ƃ������ƂŊJ�u�������܂��B �Ƃ͌����Ă��A���͂���Ӗ��u���ł����v�ł��̂ŁA���낢��m���Ă���悤�ł��āA�ЂƂ̎�ށi�Ⴆ�V���N����j�ɍi�����Ƃ��́A�������Đ[�����Ƃ͒m��܂���B�i�����������o��������܂���B�j����͍ŏ��ɔ��Ă��܂��܂��B �������A�u���Ⴀ�A���������N�������Ă����H�v�ƌ������ƂɂȂ�ƁA�l���Ă݂���A���ȊO�A�N�����Ȃ����ƂɋC�����܂��B�����Ȃ�ƁA���̃X�N�[�����J�u����̂́A�K�s�K�ɂ�����炸�A���̋`���ł�����킯�ł��B ���̂悤�Ȏ�|�ł��̂ŁA��u���ȂǂƂ������͈̂���������܂���B(�j�@��������u��������Ȃ����A�F����̂����R�ł��B ���k����́A�E�������킩��Ȃ�������A���̓��ł͉��N�̃v���Ƃ������܂ŁA�獷���ʂł��B �����ŁA���̃X�N�[���̕��j�Ƃ��ẮA�u����Ƃ͑S���W�Ȃ���Ђ��N�ސE���āA���ꂩ��̐l�����A�]�ʃr�W�l�X�Ő����Ă������B�v�ƌ�������z�肵�����e�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B ���������āA�m����o���̂�����ɂƂ��ẮA�ދ��ł܂�Ȃ����̂ɂȂ邩������܂��A�ǂ������e�͂��������B �܂��A���̃X�N�[���̓��e�́A�������A�������A�P�N�������č���Ă�������ł��̂ŁA�p�ɂȍX�V�͂Ȃ��Ǝv���܂��B�C���Ɋ��������҂����������B ���āA����ł́A��ꎞ�Ԗڂ��n�܂�܂��B |
| �P���Ԗ����]�ʂ̊�{�́u�R�s�[�v�ł��B |
| �Q���Ԗ����R�s�[�̌��� |
| �R���Ԗ��������R�s�[�ƃJ���[�R�s�[ |
| �P���Ԗ����]�ʂ̊�{�́u�R�s�[�v�ł��B |
�]�ʂ���Ƃ����Ă��A�����Ȃ���Ύn�܂�܂���B���́u���v�������Ƃ��Ă���A���h�ȍ�i�����܂����A���������ƁA�o���オ������������Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���́u���v�����̂̓R�s�[�@�A�܂��̓��[�U�[�v�����^�ł��B ���ꂩ��F���������邢�낢��ȃg���u����A�i�������E����v�f�́A�قƂ�ǂ����́u���v�Ɋւ���Ă��܂��B�����������Ӗ��ŁA���������u�R�s�[�v�Ƃ͉�����A�Ƃ������Ƃ�m���Ă������Ƃ͔��ɑ�Ȃ��Ƃł��B �ڂ��������n�߂�ƁA�����{���P�����ɂ��Q�����ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂����A�w�҂ɂȂ낤�Ƃ����킯�ł͂���܂���A�̐S�Ȃ��Ƃ����������Ă����Ηǂ��Ƃ������ƂŁA�]�ʃr�W�l�X�ɂƂ�킯�W�̂���ł��낤���e�ɍi���āA�Ȃ�ׂ��ȒP�ɏq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B |
| �@�R�s�[�@�̐��\�����E����̂́u�g�i�[�v�ł� |
���낢��ȃ��[�J�[����o�Ă���R�s�[�@��[�U�[�v�����^�̉��i���ׂĂ݂Ă��������B�����ɋ��ʂ����������ł���Ǝv���܂��B����́u�R�s�[�X�s�[�h�������قǁA�l�i�������v�Ƃ������Ƃł��B �Ԃ������ł���ˁA�����\�Ƃ����̂́A�����ނˏo����X�s�[�h�̂��Ƃ������Ă��܂��B�R�s�[�̐��E���A�̂���A�����ɑ�����R�R�s�[�ł��邩�̋����ł����B �Ƃ���ŁA�����R�s�[���ł��邽�߂ɂ́A�Ȃɂ��d�v���Ǝv���܂����H �u�@�B�𑬂�������������Ȃ��́H�v�Ƃ����̂́A���]�Ԃ̐��E�ł��B�Ԃ�R�s�[�͂����͂����܂���B������X�s�[�h�������Ă��A������ƃn���h���������]�|���Ă��܂�����A�^�C�����j�Ă��܂�����ł́A���b�ɂ��Ȃ�܂���B �R�s�[�@�ɂ������āA���[�^�[�𑬂��������Ă��Ⴀ��܂���B�ԂɂƂ��Ẵ^�C���Ɠ������A�g���ޗ����@�B�̑����ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̍ޗ��Ƃ́A���킸�����ȁu�g�i�[�v�ł��B ���Ƃŏڂ����q�ׂ܂����A�g�i�[�Ƃ����̂́A�F�̒������v���X�`�b�N�̕��ł��B�v���X�`�b�N�͔M��������ƁA�n���Đڒ������o�܂��B���̏�ɏ���������g�i�[�̉摜���A�蒅���̔M���[���[�̊Ԃ�ʂ邱�Ƃɂ���āA�M���������A�n���Ď��ɐڒ�����킯�ł��B �P���ԂɂP�O�O�����̃X�s�[�h�ŃR�s�[����@�B���������Ƃ�����܂����H�������ł���A�܂�ň���@���݂ł��B�o�Ă��鎆�̂P�_�����蒅����ʉ߂���̂́A���������Ƃ͂���܂��A�ق�̉��\���̂P�b�ł��傤�B�܂���������قǂ̈�u�ŁA�g�i�[�ɔM��^���ėn�����Ē蒅�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B����Ȉ�u�Œ蒅���鐫�\���������g�i�[���J������Ȃ�����A�@�B�������瑬�������āA�R�s�[�X�s�[�h���グ�邱�Ƃ͂ł��܂���B�R�s�[�̃X�s�[�h�����́A���͍����\�g�i�[�̊J�������Ȃ̂ł��B |
| �@�g�i�[�̐����͂ǂ�ǂ�ς��܂� |
�R�s�[�̃��[�J�[��������ɂȂ��āu�g�i�[�v�̊J����i�߂Ă���̂͂������肢���������Ǝv���܂��B �������g�i�[�̐��\�́u�X�s�[�h�v�����ł͂���܂���B�C���t���ꂽ��������Ǝv���܂����A�g�i�[���n���Ď��ɐڒ�����ہA�Ȃ����[���[�̕��ɂ͒����Ȃ��̂��낤�H�Ƃ������Ƃł��B ��������g�i�[�ł�����A���[���[�̕��ɂ��������Ă������Ƃ��܂��B�������A���[���[�̕\�ʂ̍ގ����A�������ɂ����f�ނɂ��邱�Ƃɂ���āA�g�i�[�����̕������ɂ������悤�ɂ��Ă���̂ł��B�������ɂ����f�ނƂ́A���������Ƃ�����Ǝv���܂����A�u�V���R���v��u�e�t�����v�Ȃǂ́A���������������ޗ��ł��B�e�t�������H���ꂽ�t���C�p���ɂ͋ʎq�Ă����������܂����ˁA���̌����ł��B �����������͂����Ă��A�������͂̑傫���u�����\�g�i�[�v�̂��Ƃł��B���ꂾ���ł͕s�\���ł��B���̂��߁A�ȑO�̓V���R���S���̔M���[���[�ɁA����ɃV���R���I�C�����܂Ԃ��āA��ɂ���������̂��A�Ƃ����قǂ̒蒅���̍\���ł����B ���������V���R���I�C���́A�Ăщ�����ďz������̂ł����A�g���Ă��������ɃS�~������������A����Ă����肷�邽�߁A���̊��Ԏg������A�T�[�r�X�}����������ĐV�����I�C���ƌ������Ă����̂ł��B���ꂪ���ɂȂ�܂����B �T�[�r�X�}���̃����e�i���X�R�X�g�̂Ȃ�Ƃ��A�͂��܂��̂Ă�I�C���Œn�����̂Ȃ�Ƃ��A����Ƀ��[�U�[�v�����^�̕��y�ŁA�R�s�[�@��������������̉��{���̐��̋@�B���s��Ɉ��āA�ƂĂ�����Ȃ����V���R���I�C�����������Ȃ�Ė������`�I�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B �����ōl����ꂽ�̂��A�g�i�[�̒��ɃI�C������ł����āA�M��������Ƃ��ꂪ���ݏo���Ă���悤�ȐV�^�g�i�[�ł��B�g�i�[�̈ꗱ�ꗱ���J�v�Z���ɂȂ��Ă���̂ł��B���[���[�ւ̃I�C���������A�g�i�[���ʂ������ƂɂȂ����킯�ł��B ���̂��߁A�g�i�[�͂��n���₷������K�v�������A�n�����g�i�[�͎��̑@�ۂ̊Ԃɂ��ݍ���ł����āA��������蒅���邱�ƂɂȂ�܂��B�i���ɂ͌��Ԃ��������I�j ���̃^�C�v�̃g�i�[���A���[�J�[�̋Z�p�͋����̓I�ł��B�R�s�[���[�J�[�≻���i���[�J�[���A���邵�̂�������ĊJ���ɂ�������ł��܂��B �Ƃ������Ƃł��̂ŁA�R�s�[�̃g�i�[�قǁA�ω��̌������ޗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ������������������Ǝv���܂��B�V�����@�킪�������ꂽ��A��������܂ł̃g�i�[�Ƃ͈Ⴄ�����ɂȂ��Ă����A�Ȃ�Ă��Ƃ͓��풃�ю��ł��B ����C���N�Ȃǂ́A�P�O�N�O�̎�ނ����ł���ɓ���܂����A���ƃg�i�[�Ɏ����ẮA�����炨�C�ɓ���̂��̂������Ă��A�����͎�ɓ���Ȃ���������Ȃ��̂ł��B �s�N�A���A����Ȑ��E�ɐg�������Ă��܂����̂ł������ςł��B�܂������C�̋x�܂�Ђ܂�����܂���B�V�����@�킪�o�����A�������܂Œʂ�]�ʂ��ł��邩�A�Ƃ��������Ƃ̌J��Ԃ��ł��B����Ȃ���ȂŁA�]�ʎ��̕����ǂ�ǂ�ς���Ă����܂��B |
| �Q���Ԗ����R�s�[�̌��� |
���e��u���āA�|���ƃ{�^���������A�X�C���Əo�Ă���R�s�[�B���̊ԁA�@�B�̒��ł͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă��邩�����m�ł����H �ŋ߂̓R�s�[�Ƃ����Ă��A�̂Ƃ͂������l�ς�肵�āA�f�W�^���J���[�R�s�[��A�p�\�R���p�̃��[�U�[�v�����^�Ƃ������`�Ŏg���Ă��܂����A��{�̊�{�͂U�V�N�O�Ə������ς���Ă��܂���B�����A�[���b�N�X�ŗL���ȁA�[���O���t�B�Ƃ����d�q�ʐ^�����ł��B ����Ƃ͈Ⴄ�����͂ǂ�Ȃ��̂����邩�Ƃ����ƁA�Ă��ƌĂ��W�A�]����A�ŋߎ嗬�̃C���N�W�F�b�g�����A���C���N���g�������̂�c�o�d�ł��Ȃ��݂̋≖�ʐ^�����Ȃǂ�����܂��B�܂��A�������������̂͂ЂƂ܂������Ă����āA�����ł́A�[���O���t�B�����ɂ��āA�K�v�ŏ����̒m����g�ɂ��Ă����܂��傤�B ����Ȗʓ|�L�����Ȓm���͂���Ȃ���A�Ƃ��������A������Ƃ����䖝���ĕ����Ă��������B�Ƃ����̂́A���ꂩ��]�ʂ̎d�������Ă����ƁA���܂��܂ȃR�s�[�̃g���u���ɑ������܂��B���̂Ƃ��ɁA���̃R�s�[�̌����Ɋ�Â����@�B�̓����@�\��m���Ă����ƁA�T�[�r�X�}�����ĂȂ��Ă��A�����ʼn��}���u���{���邱�Ƃ����肤��̂ł��B ����͏��������Ă�����Ŏ��ɏd�v�Ȃ��ƂŁA�Ⴆ�Γy�j�E���j��A�~��ꐳ���Ȃǂ́A�����炪�����ɖZ�����낤�ƁA�T�[�r�X��Ђ͗⍓�ɂ����x�݂��Ă��āA�A�������܂���B�}���̎d���̓r���ŁA����@�B���_�E�����Ă��܂�����A���͂◊���͎̂����������Ȃ��Ɋׂ�̂ł��B����ȂƂ��A�킸���Ȓm�����킪�g���~���Ă���邩������܂���B �����ł͂��܂�ڂ����b���������͂���܂���B�����A�����ǂ�ł���Ȃ邲�������킢�����́A�C���^�[�l�b�g�ŒT������A���̏��Ђ������āA�ڂ����m����悤�ɂ��Ă��������B |
| �@�R�s�[�@�̐S�����́u�����d�́v |
�����A������ςȂ��畷�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȑ��p�ꂪ�o�Ă������A�����炢�₾�ƌ������A�Ǝv���Ă�ł��傤�H ���I���ۂ��ł����ǁA�����Ă��܂��A�ȁ[�I�Ƃ����قǒP���ł��B �R�s�[�@�̒��ɂ��銴���̂ƌĂ�Ă�����̂́A���́u�����d�́v�Ƃ������̂Ȃ̂ł��B���������Ƃ���̐����������������ł��B���Ȃ킿�A�u����������ƁA�d�C��ʂ������ɂȂ镨�́v�ł��B�Ƃ������Ƃ́A�u�Â��Ƃ���ł́A�d�C��ʂ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B �ł́A���̕��́i�����̂ƌĂт܂��j�̏�ɉ摜������Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B �R�s�[�@�̒��͐^���Âł��B���̒��ɂ��銴���̂̕\�ʑS�̂ɁA�v���X�̐Ód�C���悹�Ă��܂��B�i�ѓd��Ƃ������u�ŃR���i���d����Ɠd�ׂ����̂ł��B�j �����̂̓A�[�X����Ă��܂����A�^���ÂȒ��ł�����A�Ód�C�͓������ɁA�����̂̏�ɏ�����܂܂ł��B ���ɁA���e��̏�ɒu�����������e�Ɍ��ĂāA���˂����������̊����̂ɏƂ炵�܂��B�����̕����͍��ł�����A���͔��˂��Ă��܂���B�����ȊO�̔������������������˂��Ă��āA�����̂ɓ͂��܂��B �����ȊO�̕����̌��������̂ɓ�����܂����B����ƁA���̕������������͓̂d�C��ʂ������ɕς��A�����ɂ������v���X�̐Ód�C�͗���ē����čs���Ă��܂��܂��B����ƁA�����̂̏�ɂ͕����̌`�������v���X�̐Ód�C�����c���ꂽ��ԂɂȂ�܂��B �����܂ł͂킩��܂������H�@ �����ŗp�ӂ���̂́A�g�i�[�ł��B�g�i�[�Ƃ͑O�ɂ��b�����ʂ�A�F�̒������v���X�`�b�N�̕����ł��B ���w���̂���K���܂������A�����͂�����������A�C�ꍇ���ƁA�Ód�C��тт܂��B���̃g�i�[�́A�������������@�Ń}�C�i�X�ɑѓd�����Ă���܂��B �}�C�i�X�ɑѓd�����g�i�[���A�����̏�̕����̌`�ɑѓd�����v���X�̐Ód�C�ɋ߂Â���ƁA�v���X�E�}�C�i�X�������t�������āA�����̌`�ʂ�Ƀg�i�[�������̂̏�ɂ������Ă����܂��B ����ŁA���܂ł͖ڂɌ����Ȃ������Ód�C�̕����i�Ód�����ƌĂ�ł��܂��j���A�ڂɌ�����g�i�[�̕����ɂȂ�܂��B �����Ŏ��𑗂荞��ł��A�����̂ɏd�˂āA���̗�������v���X�ɑѓd�������[���[�ň������Ă��܂��B����ƁA�g�i�[�̓}�C�i�X�ł�����A���̃v���X�̓d�C�ň��������āA���̏�ɏ��ڂ��Ă��܂��B �ǂ��ł����A�����Ɏ��̏�Ƀg�i�[�̑����ł����ł��傤�H �ł����̒i�K�ł́A���̓v���X�`�b�N�̕�����Ԃł�����A�w�ŐG��Ǝ��Ă��܂��܂��B �����ŁA���͒蒅���ɑ����A�g�i�[���M���[���[�ŗn������āA���ɒ蒅����Ƃ����킯�ł��B �������ł����H����Ȃ������ł��傤�H�@ ���Ȃ݂ɁA�����̂̕��͂��̂��ƁA���ɓ]�ʂ��ꂸ�ɂ킸���Ɏc�����g�i�[�ƐÓd�C���A�u���[�h�⏜�d��ɂ���đ|�����Ă��A���̃R�s�[�ɔ�����̂ł��B �ȏ�̍H�����܂Ƃ߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B �@�@�@�ѓd �@�A�@�I�� �@�B�@���� �@�C�@�]�� �@�D�@�蒅 �@�E�@���| ���̌����������̂��A�A�����J�̃[���b�N�X�̐��݂̐e�A�b�D�e�D�J�[���\���ł��B�P�X�R�W�N�̂��Ƃł����B |
| �@���[�U�[�v�����^�Ƃ� |
�R�s�[�@�ƈ���āA�p�\�R���p�̃��[�U�[�v�����^�ɂ́A���e���悹��K���X�䂪����܂���B����̓R�s�[�@�̃v�����g���镔��������Ɨ����������̂ƍl����悢�ł��傤�B ���e���悹�Ȃ��̂ŁA����Ɍ��ĂāA���ˌ��������̂ɏƂ炷�A�Ƃ������Ƃ͂ł��܂���ˁB�����Ŏg����̂��A���[�U�[�����ł��B ���̏ꍇ�A�܂������̑S�̂��}�C�i�X�ɑѓd�����Ă����܂��B�����ɕ����̕����ɑΉ�����ӏ��Ƀ��[�U�[�����Ă�ƁA�����̓d�C���v���X�ɕς��܂��B���̃v���X�̐Ód�����Ƀ}�C�i�X�̃g�i�[����������킯�ł��B �ŋ߂̓R�s�[�@�����[�U�[�������嗬�ɂȂ��Ă��܂�������A�f�W�^���R�s�[�Ƃ������̕��@�Ńv�����g���Ă���ƍl���Ă悢�ł��傤�B���e�Ɍ��Ă�̂́A�����̂ɓ͂��ďƂ炷���߂ł͂Ȃ��A�f�W�^���f�[�^�ɂ��邽�߂Ɍ��e��ǂݎ���Ă���̂ł��B ����ɑ��āA�̂Ȃ���̃v���Z�X�ŃR�s�[������̂��A�A�i���O�R�s�[�@�ƌĂ�ł��܂��B�i�����Ƃ����̌��t�͂قƂ�ǎg���܂��E�E�j |
| �R���Ԗ��������R�s�[�ƃJ���[�R�s�[ |
�s�N�A�̎g�p�������ɁA�u�J���[�R�s�[�@���g���āA�������]�ŃR�s�[���܂��B�v�ȂǂƏ�����Ă���ƁA�Ȃɂ��J���[�R�s�[�@���g��Ȃ��Ă��A�����R�s�[�@�ł�����łȂ��́H�Ƃ����C�����ɂȂ�܂��B�������Ƃ��ł��B �Ƃ��낪���ꂪ���ɂ��炸�B�Ⴄ��ł���A�g�i�[���B ����ł́A������Ƃ����A�u�g�i�[�Ƃ͉�����v�̂��b���������܂��傤�B �g�i�[�Ƃ́A�F�̂����v���X�`�b�N�̕��ł��B�M��������ƁA�n���Đڒ��͂������A���ɂ������Ă����킯�ł��B�@�E�E�E�ƁA�����܂ł͂��b���܂����ˁB �����R�s�[�̃g�i�[���������Ŋg�債�Č��Ă݂�ƁA�Ȃɂ��傫���Ĕ����ۂ������܂�̎���ɁA�ׂ����������̂悤�Ȃ��̂������ς������Ă���̂������܂��B �����̂̓J�[�{���u���b�N�Ƃ����痿�ł��B�����ۂ��̂́A�o�C���_�[�����ƌĂ��v���X�`�b�N�̉�ł��B�o�C���_�[�����Ƃ����̂́A�ڒ��܂̖�����������̂ł��B�|���G�X�e���Ƃ��A�A�N�����Ƃ��A�X�`�����ȂǂƂ������A�M��������ƊȒP�ɗn���ăx�^�x�^�ڒ������o��v���X�`�b�N�ł��B���̐ڒ��܂��g���āA�����J�[�{�������ɂ������Ă���킯�ł��B �b�͂�����Ƃ���܂����A�K���Ŏg���n�������悤�Ȍ����ł��B���[�\�N��R�₵���X�X���W�߂āA�j�J���Ōł߂Ă���܂��B�X�X�����ł͎��ɂ������܂��A�j�J���Ƃ����ڒ��܂��ꏏ�ɍ������Ă��邽�߂ɁA���̏�Ɏ����蒅����̂ł��B �J���[�R�s�[�̃g�i�[�������悤�Ȏd�g�݂ł����A�����́A�o�C���_�[�����ƗL�@�痿�������ĂЂƂ����܂�ɂ������̂��A�ׂ������ӂ��Ă���܂��B�L�@�痿�̐F�́A�b�i�V�A���j�A�l�i�}�[���^�j�A�x�i�C�G���[�j�A�j�i�u���b�N�j�̂S�F�ł��B�i�������ŋ߂̋@��Ɏg���Ă���V�^�g�i�[�́A�d���@�Ƃ��ŁA���ӂ����ɍ���Ă��܂��B�j �ƁA�����܂ł́u�����悤�ȁv�Ə����Ă��܂������A�����ƃJ���[�ł͌���I�ȈႢ������̂ł��B �J���[�R�s�[�͂S�F�̃g�i�[���d�˂ĈႤ�F�����Ȃ���Ȃ�܂���B�ΐF�ɂ���ɂ́A���F�i�x�j�ƐF�i�b�j���d�˂�̂ł��B���̂Ƃ��A�F�������邽�߂ɂ́A���݂��̐F���u�����v�łȂ���Ȃ�܂���B�����s�������ƁA���F�̏�ɐ��悹�Ă��A���̐F���B����āA�ɂ��������܂���ˁB �J���[�g�i�[�ŏd�v�Ȃ̂́A�u�������v�Ƃ������Ƃł��B �Ƃ��낪�����R�s�[�̃g�i�[�́A�J�[�{���u���b�N�Ƃ����A�ɂ߂ĕs�����Ȋ痿�ō���Ă��܂��B�J���[�R�s�[�̍����g�i�[�́A����ł͂܂����̂ŁA�L�@�痿�Ƃ��������ȍ��F���g���Ă���̂ł��B ���́A�������s�������Ƃ������Ƃ́A�]�ʂ�����ہA���܂��܂Ȍ`�ʼne�����y�ڂ��Ă��܂��B����ɂ��ẮA�܂����ڂ�ʂɂ��Ă������������܂��B �ŁA�����ł́A�ǂ̂悤�ȔF���������Ă����悢���Ƃ����ƁA �����܂ł��T�O�ł����A�u�����R�s�[�̉摜�͕��̏W�܂肾���A�J���[�R�s�[�̉摜�͖����`�����Ă���B�v�ƃC���[�W���Ă����Ă��������B �s�N�A�̓]�ʋZ�p�́A���́u�g�i�[�̖��v�𗘗p���āA���낢��ȋZ��҂ݏo���Ă����܂��B |