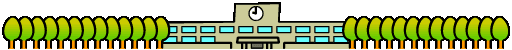 |
| スクールTOPへ | 3へ |
|
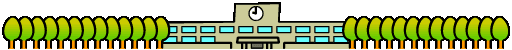 |
| スクールTOPへ | 3へ |
|
| 転写専門学校 |
| 火曜日●紙について |
| 1時間目●紙の基礎知識 |
| 2時間目● |
| 1時間目●紙の基礎知識 |
コピーや印刷とは切っても切れない関係、紙について、知っておかなければならないことをまとめてみましょう。 紙の知識といっても、いろいろあって、ここではとうていまとめきれませんので、よいサイトを見つけましたので、必要に応じてそちらをごらんください。 「紙の博物館」 「紙のサイズ・厚さ・種類など」 「紙豆知識」 ここでは、そのなかでも特に我々のビジネスに関係の深いものだけを取り上げてみます。 1.コピー用紙について 2.転写用紙について 3.転写する素材としての紙 |
| 1.コピー用紙について |
コピー用紙は、一目見ただけでは印刷用の上質紙と見分けがつきませんが、特にカラーコピー用紙は、コピーがきれいに写るように特別に作られています。 ●紙の表面は、薄い色のトナーもちゃんと感光体から乗り移ってくるように、きわめて平滑に仕上げられています。 ●トナー画像を感光体から電気的に転写させるため、紙の電気抵抗が最適になるように湿度調整がされています。 ●紙送りの途中で詰まったり、曲がったり、画像が伸びたりしないように、送り方向に紙の目(繊維の方向)が走っています。これを「タテ目通し」と呼びます。 ・・・ ピクアの転写の中で、コピー用紙(普通紙)を使うケースは、金箔や白箔で色を着けたり抜いたりするときです。 このときに大事なのは、紙の表面の平滑性です。安価な紙は表面が凸凹で、凹んだところには金箔がつかず、したがって抜けがらの箔も、すっきり透明に仕上がりません。 この作業のときは、必ず「コピーメーカー純正のカラーコピー用紙」を使ってください。 |
| 2.転写用紙について |
紙の性質のなかでも、特に重要なのは「紙目(かみめ)、略して目(め)」です。繊維の走っている(並んでいる)方向で、長方形の紙の、長い方向に走っている紙を「タテ目」、短い方向に走っている紙を「ヨコ目」と呼んでいます。 製紙工場で紙が作られるとき、巨大なロールに巻かれているのですが、紙の目はそのロールの長い方向に走っています。このロールから、A1判やA2判などと、タテヨコに切り分けていくために、サイズによって目の方向が変わってきてしまうのです。 コピーしたり、転写したりするとき、この目の方向性が大いに影響してきます。いろいろなトラブルの元になるのも、目が原因になっていることが多いのです。 それでは、目がどのような現象としてあらわれてくるかをまとめてみましょう。 1.紙の腰(張りの強さ)はタテ目方向にしっかりしています。コピー機に通すときは、なるべくタテ目方向に通すと、スムーズに通ります。ヨコ目の場合、出てきたときにクルクルカールしたり、画像がぶれたりすることがあります。 2.紙に熱をかけたり、湿気を与えたりすると、ヨコ目の方向に伸びていきます。 タテ目の方向にはほとんど伸びませんから、精度を要求するような場合は、この性質をうまく利用します。 3.マルチプロセッサなどの熱ローラーに通す場合、タテ目の方向に通すと、シワが出やすくなります。紙に熱や圧力を与えると歪みが生じますが、タテ目の方向には伸びないため、歪みがシワとなって現れるのです。逆にヨコ目で通すと、紙が伸びて歪みを吸収してくれます。 (コピー機の定着ローラーなどは、タテ目通しにしてもシワが出ないように、ローラーが完全な円筒形ではなく、中央が太い太鼓状に作られています。) ※金箔などのフィルムにも目があると考えてください。コピーに金をつける時に、シワを防ぐ方法は、ヨコ目に通してやることです。(使用説明書参照) 紙目の方向を知るには、 ●手で紙を裂くように破ってみて、まっすぐ破ける方が目の方向です。目が横向きですと、きれいに破れません。 ●同じ紙2枚を、90℃違えて重ねて端を持ち、ぴったり重なってたわめば、下の紙がタテ方向の目です。先端が開くようでしたら、上の紙がタテ方向です。 ●紙を2つに折ってみて、スーっときれいに折り筋がつけば、その方向に目が走っています。ヨコ目ですと、シャープに折れません。 ●コピレタシートの場合は、裏に矢印が印刷されています。矢印の方向に目が走っています。 |